遺産分割における預貯金の取り扱い
被相続人の遺産に預貯金が含まれる場合には、遺産分割においてどのように取り扱われるかご存知でしょうか。 平成28年の最…[続きを読む]
東京弁護士会所属、千代田区の弁護士事務所。法律相談を承ります。

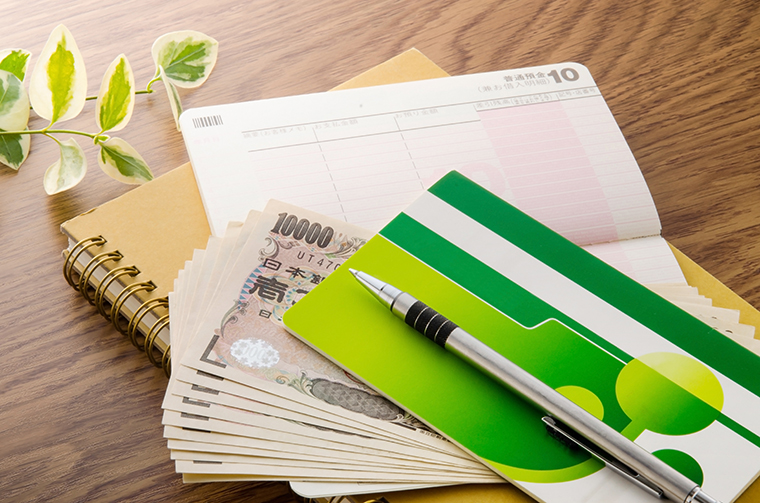
2019年7月1日施行の改正相続法により、新たに遺産分割前の相続預金の払戻し制度がスタートしました。
それまでは、遺産分割前には相続人単独では相続預金の払い戻しを受けることができず、当面の生活費の支払いや葬儀費用の支払いなどに対応できないなどの不都合が生じていました。
しかし、遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用すれば、(一定の上限はあるものの)相続人単独で相続預金の払い戻しが可能になり、当面の資金需要に対応することができるようになりました。
今回は、遺産分割前の相続預金の払戻し制度の利用方法や留意点、弁護士に依頼するメリットなどについて解説します。
目次
相続発生後に被相続人名義の預貯金を引き出すと、トラブルの原因になる可能性があります。
被相続人の死亡により、被相続人名義の預貯金は相続人全員の共有になります。よって、原則として相続人全員の同意がない限りは、被相続人名義の預貯金を引き出すことはできません。
通常は、預貯金口座の名義人の死亡を金融機関が知ることにより預貯金口座が凍結されますので、相続人により勝手に預貯金が引き出すことができない状態になります。
しかし、預貯金口座が凍結されるタイミングによっては、凍結前に相続人によって預貯金が引き出されてしまうことがあります。
このような相続発生後の預貯金の引き出しは、他の相続人から預貯金の使い込みなどを疑われて民事上のトラブルに発展するリスクがあります。
そのため、相続発生後に勝手に相続財産である預貯金を引き出すのは避けるべきでしょう。
相続発生後に預貯金口座が凍結されてしまうと、特に同居家族の当面の生活費の支払いや、葬儀費用の支払いに困る方も多いと思います。
相続人全員の合意により預貯金を引き出すことはできますが、非協力的な相続人がいると簡単には合意が得られないでしょう。
そのような場合に利用できる制度としては、以下の2つの制度が挙げられます。
本コラムでは、このうち「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」について解説します。
早速ですが、以下では遺産分割前の相続預金の払戻し制度の概要や利用条件、制度を利用する流れなどについて説明します。
その名のとおり、遺産分割協議が成立する前であっても、各相続人が単独で相続預金の払い戻しを受けることができる制度です。
被相続人が亡くなると被相続人名義の預貯金口座は凍結されてしまうため、原則として、相続人全員の合意がなければ預貯金の払戻しを受けることができません。
しかし、非協力的な相続人がいたり、音信不通の相続人がいるような場合には、すぐに合意を得ることができず、被相続人と生計を共にしていた相続人が当面の生活費に困ったり、葬儀費用の支払いができないなどの事態に直面してしまいます。
このような問題を解消するために、2019年7月1日施行の改正相続法により、新たに導入された制度が「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」です。
遺産分割前の相続預金の払戻し制度は、相続人であれば誰でも利用できますので、特別な利用条件はありません。
ただし、同制度を利用して相続預金を払い戻す場合、払戻し金額に上限が設定されています。
遺産分割前の相続預金の払戻し制度により払戻しを受けられる金額の上限は、以下のような計算式によって算出します。
単独で払戻しができる額=相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分
ただし、同一の金融機関からの払戻しは、150万円が上限になります。
遺産分割前の相続預金払い戻し制度を利用する場合、以下のような流れで手続きを行います。
まず、制度を利用するには以下のような書類が必要になります(但し金融機関によって書類が異なる可能性があるので、問合せが必要です)。
上記の必要書類が準備できたら、金融機関の窓口で相続預金の払戻しの手続きを行います。
家庭裁判所の保全処分による払戻し制度とは異なり、裁判所の手続きを経る必要がありませんので、迅速に相続預金の払戻しを受けることができるというのがこの制度のメリットです。
遺産分割協議前の預金の払戻し制度を利用する際には、以下の点に注意が必要です。
払戻しを受けた預貯金を生活費などに費消してしまうと、「単純承認」があったものとみなされてしまうため、相続放棄をすることができなくなってしまいます。
被相続人に多額の借金がある場合でもそれを相続しなければなりませんので、遺産分割協議前の預金の払戻し制度を利用するかどうかは、慎重に検討しなければなりません。
遺産分割協議前の払戻し制度を利用して払戻しができる金額には、上限が設けられています。
そのため、それ以上の金額が必要になる事情があるときは、遺産分割協議前の預金の払戻し制度ではなく、家庭裁判所の保全処分による払戻し制度を利用した方がよいでしょう。
被相続人が遺言を残している場合には、遺言の内容が優先されます。
そのため、例えば特定の相続人にすべての遺産を相続させる旨の遺言があった場合は、他の相続人は預貯金の払戻しをすることができません。
遺産分割協議前の預金の払戻し制度を利用して相続預金の払戻しを受ける場合、各相続人が単独で手続きを行うことができますが、相続トラブルを回避するためにも事前に他の相続人に連絡しておいた方がよいでしょう。
なぜなら、他の相続人は、勝手に相続預金を引き出されたとの疑いを抱きますので、その後の遺産分割協議において相続人同士の対立を招く原因になるからです。
事前に払戻し制度を利用すること、および払戻しを受けた相続預金の使途などを伝えておけば、このようなトラブルを回避することができます。
預金引き出しをする場合、弁護士に相談または依頼するのがおすすめです。
遺産分割協議前の預金の払戻し制度は、遺産分割協議が成立する前であっても相続人単独で預貯金の払戻しを受けられるというメリットがありますが、相続放棄ができなくなる、払戻し金額に上限があるなどのデメリットもあります。
安易な制度の利用は、その後の相続手続きに悪影響を及ぼす可能性もありますので、事前に弁護士に相談してから手続きを進めるべきでしょう。
弁護士に相談すれば、具体的な状況を踏まえて遺産分割協議前の預金の払戻し制度を利用するべきかどうかアドバイスをしてくれますので、制度利用による不利益を回避することが可能です。
遺産分割協議前の預金の払戻し制度を利用して相続預金の払戻しができる金額には上限が設けられていますので、具体的な状況によっては、遺産分割協議前の預金の払戻し制度では資金需要に対応できないケースもあります。
そのような場合には、家庭裁判所の保全処分による払戻し制度を利用する必要がありますが、これは専門的な手続きになりますので弁護士によるサポートが欠かせません。
迅速に手続きを進めるためにも、家庭裁判所の保全処分による払戻し制度については、弁護士に任せるべきでしょう。
ここまでご説明した遺産分割協議前の預金の払戻し制度は、あくまでも当面の資金需要に対応するための制度に過ぎませんので、その後は遺産分割協議を行い、その他の相続財産の分け方を決めていかなければなりません。
遺産分割協議の場面では相続人同士の対立からトラブルが生じる可能性が高いため、スムーズに話し合いを進めるためにも弁護士に依頼するのがおすすめです
弁護士に依頼すれば代理人として遺産分割協議に対応してもらえますので、公平妥当な遺産分割案を提案することが期待でき、他の相続人の納得も得られやすいといえるでしょう。
被相続人が亡くなると被相続人名義の預貯金口座は凍結されてしまいますので、相続人全員の合意がなければ払戻しをすることができません。
相続人の同意が得られず、相続預金の払戻しができない状態が続くと当面の生活費や葬儀費用の支払いができなくなるおそれがあるため、遺産分割協議前の預金の払戻し制度を利用してみるとよいでしょう。
ただし、遺産分割協議前の預金の払戻し制度には、メリットだけでなくデメリットもありますので、制度を利用するべきかどうかも含めて、一度、専門家である弁護士に相談してみるとよいでしょう。
相続発生後の問題解決については、ぜひあたらし法律事務所の弁護士にご相談ください。

〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町3-30
WIND KIOICHO BLDG.
(旧:紀尾井町山本ビル)5F
東京メトロ「麴町」駅1番出口より徒歩約5分
東京メトロ「永田町」駅5番・9番・7番出口より徒歩約5分
東京メトロ「赤坂見附」駅D番出口より徒歩約8分
東京メトロ「半蔵門」駅1番出口より徒歩約8分
JR「四ツ谷」駅麹町口より徒歩約14分